こんにちは!青じそです!
今回は京大物理についての記事です!
「京大の物理ってなんだか難しそう」
と思う人もいるかもしれませんが、基本がしっかりできていれば6,7割は取れるレベルですのでしっかり対策して勉強していきましょう!
青じそ
夏の模試ではE判定でしたが、現役で京大に合格し京大農学部に通っています。
勉強法や使っていた問題集・参考書を紹介しています!
京大物理の構成
京大の物理は大問3つで構成されています。
毎年大問1は力学、大問2は電磁気、大問3は熱力学、波動、原子のいずれか、または複合問題が出題されます。
力学、電磁気はほぼ必ず出るのでしっかり勉強しておく必要があります。
また多くの問題は共通テストと同様に文章中の語句や数字を埋めていく穴埋め式になっています。
大問の最後にはそれまで解いていた文章を踏まえての問題があり、記述やグラフを描く問題もあります。
京大の過去問をここに載せることは著作権的にできませんが、京大のホームページで見られるので過去問を見たい人はこちらから見てください。
一般選抜の試験問題等 | 京都大学 (kyoto-u.ac.jp)
京大物理の傾向・特徴
傾向
力学・電磁気は毎年、熱力学・波動・原子はバランスよく出題される
京大物理の傾向として力学・電磁気は毎年出題され、もう一つの大問は熱力学、波動、原子の中からバランスよく出題されます。
そのためどの分野もしっかりと勉強しておく必要があります。
力学
力学では円運動、単振動の問題がよく出題されます。
またそのような運動の中でも2物体を扱う問題が多いです。
2物体を扱う問題は得意な人と不得意な人で差が出やすい問題なので2物体の運動はできるようにしておくのがよいです。
電磁気
電磁気ではコンデンサー、電磁誘導の問題がよく出題されます。
コンデンサーも電磁誘導も研鑽が複雑になることがあります。
そのため物理の現象を理解すること、量の多い計算を正しく速く行えるようになること両方が重要です。
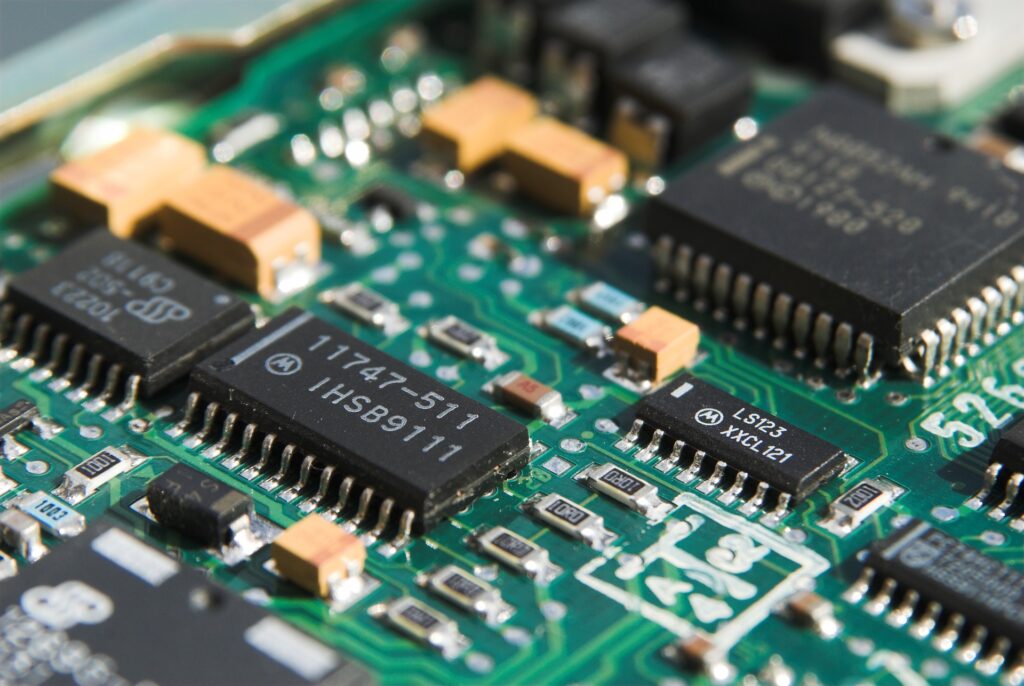
熱力学
熱力学では断熱変化の問題がよく出題されます。
断熱変化はポアソンの式をしっかりと理解し、使いこなせるようにしておいてください。
熱力学は範囲が狭く問題も難しくしにくいので安定して高得点を狙いたいです。
波動
波動では光波がよく出題されます。
そのなかでも光の干渉や回折格子などがよく出題されています。
また音波と光波の複合問題も出題されるので公式をきちんと理解しておきましょう。
原子
原子では光の粒子性の問題がよく出題されます。
力学の知識が必要になる場合もあるので力学の問題が解けるようになってから原子の問題を解いていきましょう。

特徴
穴埋め問題が多い
京大物理の大きな特徴として「文章中の穴埋め問題が多い」ことがあげられます。
穴埋め問題が多いということは途中の部分点がもらえないということです。
どれだけ途中までの計算が合っていても答えが合っていなければ点数がもらえないので計算間違えのないようにしっかり確認しましょう。
また問題を進めていく上で前の問題の答えを使うことが多いので物理のケアレスミスは致命的です。
問題文が長い
次の特徴として京大物理は「問題文が長い」ことがあげられます。
穴埋め問題が多いとそれに伴って問題文が長くなってきます。
そのため「今何の話をしているのか」「どの文字を使って答えるのか」「どの部分を利用して解答を導くのか」をしっかりと理解して問題文の誘導に乗る必要があります。
この形式を扱っている問題集がほとんどないので最初は慣れないかもしれませんが、過去問を解いていくうちになれるのでそこまで気にする必要はありません。
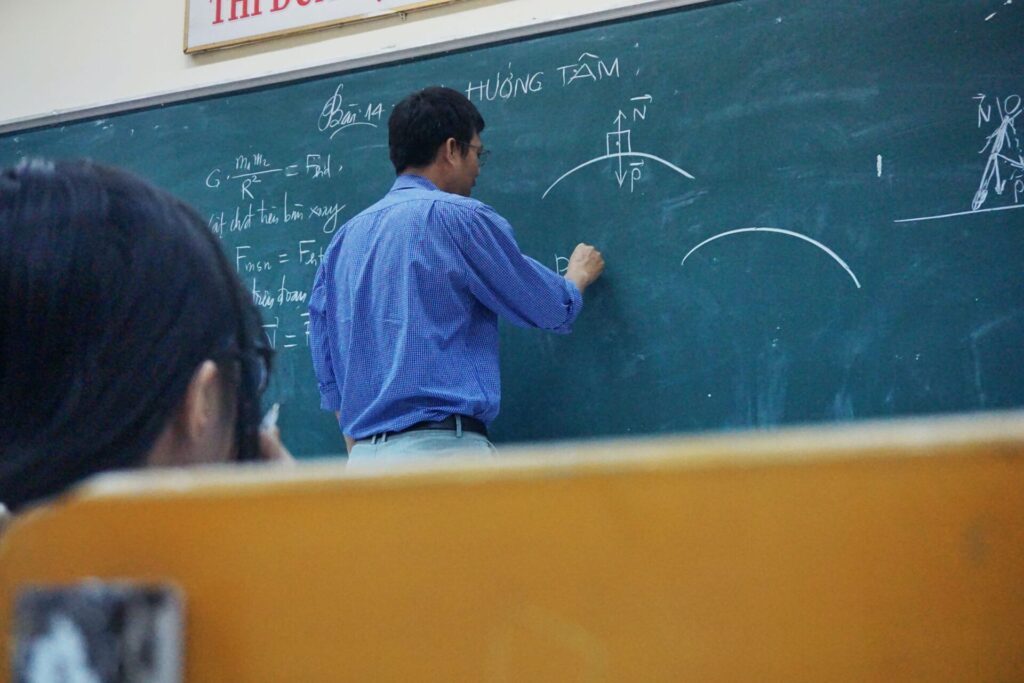
京大物理の対策・勉強法
問題集
物理の勉強で使用していた問題集は以前に紹介したので気になる方はこちらからお願いします!
高校時代に使っていた物理の問題集・参考書はこちらから!
基本をしっかりとやる
どの教科でも言われることですが、とにかく基本が大事です。
特に京大のような穴埋め問題でははじめの方で間違えてしまうとそこからの問題も連鎖的に間違えてしまうことがあります。
また最後の方になると難易度の高い問題もありますが、はじめは簡単な問題が多いので基本的な部分が解けるだけでもある程度点数は取れます。
そのため焦らずに基本的な部分から力をつけていくことが重要です。
また公式を単に覚えるのではなく、その公式はどのように導かれたのか、その公式はどんなことを意味しているのかということまで考えておくと難しい問題でも解きやすいと思います!
長文になれる

京大物理の特徴としてもあげましたが、京大物理は問題文が長いです。
僕はセンター物理で100点を取れましたが(自慢)、京大の物理はあまり解けませんでした。
なぜかというと京大の長文に慣れていなかったからだと思います。
しかし何年も過去問を解いていくうちにだんだんと形式に慣れていき、8割を安定して取れるようになりました。
これに関しては慣れなのである程度物理の力がついたらあとは過去問あるのみだと思います。
また共通テストの問題も穴埋め形式の問題が多く、京大物理を短く簡単にしたものなので形式に慣れるという観点では共通テストの物理を行うのもオススメです。
最後まで諦めない
最後は「最後まで諦めない」です!
「いきなり精神論かよ(笑)」と思った人、ごめんなさい。
京大物理の問題は長い文章で問題が続いているので一つつまずくとそこからの問題はなかなか解けません。
しかしたまに設定を変えて考える問題だったり、前の問題とは関係ない話をするときがあります。
そのような場合は前の方にわからない問題があっても、後半の問題を解くことができる場合があります。
そのため問題が解けないときにその大問全てを捨てるのではなく、最後まで問題文を読んで解ける問題がないか注意深くみてください。
おわりに
いかがだったでしょうか?
物理は解けるようになると安定して高得点が狙える反面、わからないと全く解けずつまらないと思う人もいると思います。
物理は現象を数式で表したものなので簡単なものからどのようなことを言っているのか理解しながら少しずつ進めていきましょう!



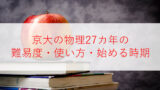
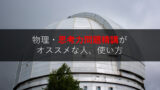


コメント