こんにちは!青じそです!

過去問っていつ始めたらいいの?
こう思った人はいませんか?
そこで今回は過去問を始める時期、使い方について紹介しようと思います!
青じそ
夏の模試ではE判定でしたが、現役で京大に合格し京大農学部に通っています。
勉強法や使っていた問題集・参考書を紹介しています!
過去問を始める時期
過去問を始める時期として、理想、標準、最低ラインは以下の通りです。
| 時期 | |
| 理想 | 9月頃 |
| 標準 | 11月頃 |
| 最低ライン | 共通テスト後 |
当たり前なこととして過去問を早く始められるなら早く始めた方が良いです。
また過去問は1回だけでなく、何回もできるならやった方が良いです。
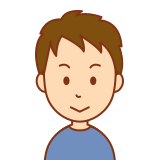
過去問の解いた年数と合格率には相関があると思う!
しかし過去問を解くために十分な力がついていることが条件です。
過去問は最後の最後の総仕上げのように思われがちですが、過去問を行いながら学力も伸びていくので過去問をやろうか迷っているなら一回チャレンジしてみましょう!
9月から始められる人
9月から始められる人は目安でいうと模試でA判定を取っているような人です。
学習範囲は終わり、応用問題もある程度解けるようになっていたら、過去問を始めても問題ありません。
過去問を解いて、直しをするのは時間がかかるので1日で全ての科目を解く必要はありません。
少しずつでいいので取り組んでいきましょう。
特に平日は学校や予備校の授業がある人は休日などまとまった時間が取れる日に行うのがよいでしょう。
12月の中旬くらいからは共通テストの勉強をするのでそれまでに10年分くらい解き、京大の形式に慣れてください。
1週間に1年分解ければ12月中旬までに10年分解き終わります。
共通テストが終わったら、もっと遡ったり、過去問の2周目に入ったり、京大模試を解いたり、苦手な分野の特訓に当てたりなど比較的余裕を持てます。
もし余裕があるなら夏休みから始めてもいいです。
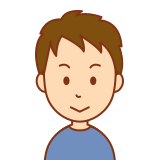
9月から始められる人はそれだけでアドバンテージ!
逆にやることなくなっちゃうかも(笑)
11月から始められる人
9月から始められない人は11月から過去問を始めることを目標に勉強してください。
11月初めから1週間に1年分解くと12月中旬までに6,7年分解くことができます。
そこから共通テストの勉強をし、共通テスト終わりから過去問を再開すると最低でも10年分は解けます。
そこからはもっと遡ったり、過去問の2周目に入ったり、京大模試を解いたり、苦手な分野の特訓に当てたりしてください。
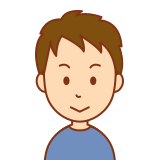
11月から始めても余裕がある!
共通テスト後から始める人
過去問を始めるタイミングとして最低ラインは共通テスト後です。
共通テストが終わってから二次試験まで1ヶ月と少ししかないのでちょっと急いで過去問をやらなければいけません。
二次試験までに最低でも5年分は解いておきたいので、共通テストが終わったらすぐに二次試験の対策を始めましょう!
自分はまだ過去問を解くレベルにないと思っている人でも
「自分に合ったレベルの問題集をやった後、2,3年分しか過去問を解けない」のと「多少過去問は自分に難しいけど10年分解いた」では後者の方が点数は取れます。
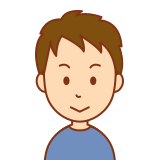
解かなくてもいいので、共通テスト前に見ておくだけでもやっておいた方がいい!
過去問の進め方
赤本と青本どっち?
過去問には通称「赤本」と呼ばれる教学社が出しているものと「青本」と呼ばれる駿台が出しているものがあります。
| 赤本 | 青本 | |
| 掲載年数 | 7年 | 5年 |
| 値段 | 2310円 | 2420円 |
| その他 | 解説は青本に比べ不親切 | 解説は赤本に比べ親切 |
掲載年数が多く、値段も安い赤本の方がコスパは良さそうですが、解説は青本の方が丁寧なので青本をオススメします。
ただ5年より前の問題を解こうと思うとなかなかそれ以前のものは売っていません。
メルカリなどのフリマサイトを見ると青本より赤本の方が売られているのでその場合は赤本を使用しても問題ありません。
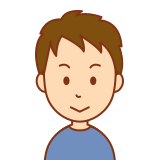
メルカリは安いからオススメ!
新しい年度から?古い年度から?
過去問を進める際、新しい年度から行うか、古い年度から行うかの2通りがあります。
どちらが良いかというと5年分くらいならどっちからでもいいです。
5年くらいではあまり傾向なども変わらないのでどちらからやっても良いです。
ただ10年分くらいを一通りやろうとすると問題の傾向なども変わってくるので新しい方から行い、京大の問題がどのようなレベルなのか、どのような形式なのかを早めに知っておいた方が良いです。
新しい年度から行うメリットとして、傾向やレベルが自分の受ける年度と近いことや2周目をやる際にまた最新年度から行うことができることがあげられます。
(2周目を行うのが10年前からだと最新年度までできない可能性もあるからです。)
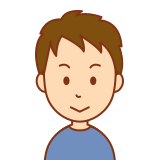
過去問に時間が取れないなら新しい年度からがオススメ!
また古い年度から行うメリットとして京大の問題になれてきたところで最新年度を解くことができます。
京大の形式に慣れることを重要視する人は最新年度から、京大の過去問で実際に自分の実力を試したい人は古い年度(5年前くらい)から行うとよいでしょう。
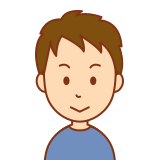
慣れてからやることで本番に近い状況で解けます!
27カ年はどう使う?
過去問を扱っている問題集として「27カ年シリーズ」があります。
- 27年分の問題が掲載
- 年度別ではなく、単元ごとにまとめられている
- 巻末に年度と問題番号が載っているため年度ごとに解くことも可能
しかし年度別に解こうとすると一回にかなりの時間が必要になります。
そのため27カ年は空いた時間でもできるように1つずつ問題を解いていくことがオススメです。
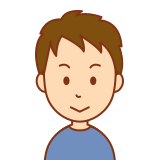
本番に近い練習は赤本や青本で、自分の苦手な範囲の部分練習は27カ年でやるのがオススメ!
過去問は印刷しよう!
赤本や青本などを使う際には問題を印刷するのがオススメです。
数学や理科はどちらでも良いですが、国語や英語は印刷した方が良いです。
なぜかというと赤本や青本は分厚いため書き込みがしにくい、ページの大きさが小さいため書き込みがしにくい、2周目を行うときにきれいな状態でできるからです。
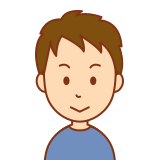
受験が終わった後に後輩にあげたり、古本屋に売るときに書き込みがない方が好まれます(笑)
模試を活用しよう!
過去問はその大学の傾向やレベルにあった問題集として優れていますが、大手予備校が行っている模試もとても有効です。
河合塾が行っている京大オープン、駿台が行っている京大実践、代ゼミの京大プレ、東進の京大本番レベル模試があります。
これらを受けるのもいいですし、河合塾と駿台は1年前の京大模試を集めた問題集を出版しています。
科目ごとに分かれているので自分が不安に思っている科目、または得意でもっと点数を伸ばしたい科目だけでもいいのでやってみるのがオススメです。
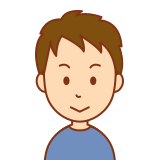
各塾が模試として出した問題とあって、普通に勉強になります(笑)
おわりに
いかがだったでしょうか?
過去問はあらゆる勉強の中でも最重要の勉強です。
自分にとって一番力になる方法で過去問を行っていきましょう!



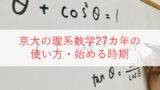
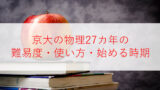

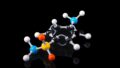
コメント